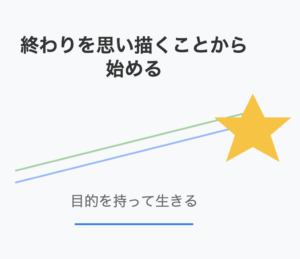【理論と実践】「7つの習慣」第1の習慣:主体的に生きるということ
~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和7年2月12日 医療・介護経営の理論と実践 2467号
■「7つの習慣」第1の習慣:主体的に生きるということ
中神勇輝(なかがみゆうき)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。中神です。
最近の読み物は、名著「7つの習慣」です。
正式な本の名前は、
「完訳 7つの習慣 人格主義の回復: Powerful Lessons in Personal Change」です。
(スティーブン・R・コヴィー、フランクリン・コヴィー・ジャパン)
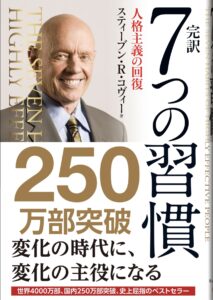
ということで、行動に落とし込んでいくために、一つずつ振り返っていきたいと思います!
自分の人生の主導権を握る、それが第1の習慣「主体的である」の本質です。
今回は、この重要な習慣についてポイントを解説していきます。
■ 刺激と反応の間にある選択の自由
私たちの人生には様々な「刺激」が存在します。
周囲の環境、他人の言動、予期せぬ出来事など。
でも重要なのは、その刺激に対して「どう反応するか」は自分で選べるということ。
これが「主体的である」の核心です。
■ 影響の輪と関心の輪
私たちが抱える問題には、自分でコントロールできるものと、できないものがあります。
効果的な人は、自分の「影響の輪」、つまり自分が直接影響を与えられる範囲に集中します。
コントロールできない問題に対しては、その状況への「反応の仕方」を変えることで対処します。
■ 約束を守る日々を過ごす
主体性を身につける具体的な方法の一つは、
小さな約束を自分に対して、あるいは他者に対してして、それを守ることです。
これにより、自分の内面に誠実さが芽生え、自制心が育ちます。
■ 言葉遣いを変える
「~しなければならない」「できない」といった受け身の言葉を、
「~することを選ぶ」「~したくない」という主体的な表現に変えることで、
自分の選択の自由を意識できます。
■ まとめ:人生の作者になる
第1の習慣は、自分の人生の「作者」になることを教えています。
環境や他人のせいにするのではなく、自分の反応を選択する自由を行使し、
積極的に行動を起こすこと。
それが「主体的である」という習慣の真髄なのです。
30日間、影響の輪の中のことだけに取り組む実践を通じて、
この習慣を身につけていくことができます。
主体的に生きるということは、時に困難を伴いますが、それは同時に、
自分の人生を本当の意味でコントロールできるようになるための第一歩なのです。

以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)
◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
https://wakuwaku-kokoro.net/
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)
https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A
この記事を書いたのは、こんな人。
ーーーーーーーーーーーーーーー
中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士(登録申請中)、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。