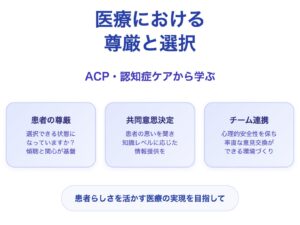【理論と実践】キャリア形成における院内・外との「人との関わり」の重要性
~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和7年9月11日 医療・介護経営の理論と実践 2677号
■キャリア形成における院内・外との「人との関わり」の重要性
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。中神です。
最近、医事課の業務にフォーカスしています。
今後は、医事の請求・会計業務という内容に入っていく予定ですが、
その前に、セミナーに参加したので、その学びをシェアします。
今回の学びは、キャリア形成における「人との関わり」の重要性です。
■偶然を活かす
キャリア形成における「人との関わり」と
「チャンスを掴む」ということの重要性について深く考えさせられました。
印象的だったのは、「計画された偶発性理論」の考え方です。
キャリアの8割が偶然によって決まるという事実は、
カチカチの人生設計では、成長は得られず、普段の「意識」こそ、
大事という示唆であると感じます。
普段持つべき「意識」は、
好奇心・持続性・楽観性・柔軟性・冒険心という5つの要素です。
これらを意識することで、偶然の出来事を自分の成長につなげられるという視点は、
非常に実践的です。
■上司をマネジメントする
また、「上司をマネジメントする」という発想の転換も興味深く感じました。
上司を管理する、ということではなく、上司を敵対視するのではなく、
同じ目標に向かう「仲間」として捉え、
その強みや弱みを理解して積極的に関わっていく姿勢は、
職場での人間関係を改善する可能性があります。
■「弱い」紐帯の「強さ」
「弱い紐帯の強さ」理論も印象的でした。
身近な人から学ぶことも多いですが、
たまに会う人や異なる分野の人からこそ新しい情報や機会も得られます。
SNSや学会参加から得られる学びや出会いを通じて、
人との関わりを「武器」に変える具体的な思考、取り組みについて
知ることができる貴重な内容でした。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)
◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
https://wakuwaku-kokoro.net/
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)
https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A
この記事を書いたのは、こんな人。
ーーーーーーーーーーーーーーー
中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。