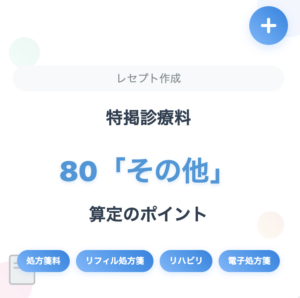【理論と実践】レセプトと画像診断、稼働率への視点(医療事務)
~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和7年9月25日 医療・介護経営の理論と実践 2691号
■レセプトと画像診断、稼働率への視点(医療事務)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。中神です。
今回は、実際のレセプト作成における具体的な点数算定のうち、
特掲診療料の「70 画像診断」について見てみましょう。
■レントゲン、CT、MRI
皆さんに馴染みがある項目が多いと思います。
レントゲン、CT、MRIですね。
レントゲン撮影を実施できるのは、誰でもできる訳ではありません。
医師、歯科医師、放射線技師。
撮影部位の場所、数に対して、
適切なレセプト病名がなければ、査定や返戻の対象となるため、
症状に応じた適切な実施、疑い病名の設定が必要です。
撮影料、診断料に加えて、
造影剤使用時の加算や画像の電子管理に対する加算などがあります。
CT、MRIにも同様に、造影剤の加算があります。
■経営への影響
CT、MRIは、点数としては高く設定されていますので、
しっかりと運用することで収益額は大きくなりやすいです。
また、点数の種類がシンプルで、月次による変動が起きにくい診療区分であり、
そのため、変動した場合にはチェックが必要ですよね。
また、稼働率が低い場合の対策も分かりやすく、大きく2つあります。
院内からのオーダーを促すことと、
機械の共同利用といった院外から利用してもらえるような運用(地域連携)や
外部サービス・仕組みを利用することです。
設備は、眠らせてしまっては何も生みません。
稼働するようにオーダーを出す、体制を整えて地域に発信していきたいものです。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)
◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
https://wakuwaku-kokoro.net/
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)
https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A
この記事を書いたのは、こんな人。
ーーーーーーーーーーーーーーー
中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。