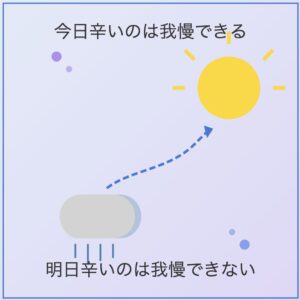【理論と実践】人事評価の裏側:評価者の視点から考える
~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和7年4月12日 医療・介護経営の理論と実践 2525号
■人事評価の裏側:評価者の視点から考える
中神勇輝(なかがみゆうき)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。中神です。
先日、娘の小学校の入学式。
アトピーがひどかった乳幼児期を乗り越え、今はすっきり。
元気に式に向かう姿に喜びを感じます。
■自己評価と上司評価の興味深い関係性
さて、今日は人事評価について、評価する側の立場から考えてみたいと思います。
多くの企業で導入されている人事評価制度では、まず被評価者が各項目について自己評価を行い、
その後、上司がそれを参考にしながら最終的な評価を決定するというプロセスが一般的です。
特に興味深いのが、被評価者が記入する自由コメント欄の内容です。
スタッフがなぜその評価を自分につけたのか、その理由や背景が綴られているこの部分は、
上司にとって非常に貴重な情報源となります。
■意外な発見:自己評価のギャップ
実際の評価作業を進めていると、様々な興味深い現象に出会います。
例えば、本来ならもっと高く評価されるべきスタッフが、自分を低く評価していることがあります。
逆に、改善の余地がある部分について、過大に自己評価しているケースも見られます。
このギャップこそが、上司が部下を理解する上での重要なヒントになります。
「なぜ彼女は自分の成果をそこまで低く見積もるのだろう?」
「なぜ彼はこの部分を高く評価しているのだろう?」という気付きが生まれることで、
部下の思考や価値観を知るきっかけになります。
■対話のきっかけとしての評価プロセス
自己評価と上司評価の差異は、単なる数字の違いではありません。
それは対話の入り口なのです。
評価面談では、この差異について話し合うことで、お互いの認識のずれを埋め、
より良い関係性を構築する機会となります。
「あなたはこの項目を低く評価していましたが、
私から見ると非常に価値のある貢献をしていると思います」というような会話から、
新たな気づきが生まれることも少なくありません。
■可視化がもたらす気づきの価値
人事評価の本質的な価値は、日々の業務や成果を文字や数値として可視化することにあります。
口頭でのフィードバックだけでは見過ごされがちな部分も、文字や数値として記録されることで、
より客観的に捉えられるようになります。
これは人事部門だけでなく、経営においても同様です。
可視化することで初めて見えてくる課題や強みがあり、それが組織全体の成長につながっていきます。
評価という行為は単なる人事手続きではなく、
組織と個人が共に成長するための重要な対話のプロセスです。
文字化し、数値化することで、新たな視点からの考察が生まれる—これこそが
人事評価の隠れた価値ではないでしょうか。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)
◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
https://wakuwaku-kokoro.net/
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)
https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A
この記事を書いたのは、こんな人。
ーーーーーーーーーーーーーーー
中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。