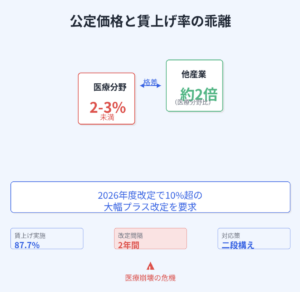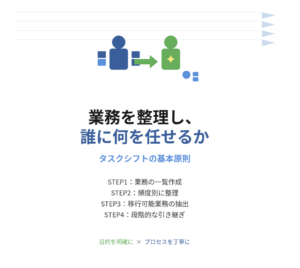【理論と実践】病院経営管理の学び 〜業務フロー図の作成〜
~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和7年11月24日 医療・介護経営の理論と実践 2751号
■病院経営管理の学び 〜業務フロー図の作成〜
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。中神です。
先日参加した病院経営管理学会で、
医療機関の業務改善に関する非常に興味深い発表がありました。
今回は、「業務フロー活用」についてです。
■業務フローとは何か
業務フローとは、業務プロセスを分解し、可視化し、図式化したものです。
「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行うのかを明確にすることで、
業務の標準化を実現します。
今回、心に残ったのは、多職種で構成されている点です。
多職種連携が叫ばれる中、診療部、看護部、薬剤部、
リハビリテーション部などの診療支援部、
そして事務部が一体となって取り組んでいます。
病院の中には、いろいろな業務があります。
その中で、何から優先して、業務フローを作成すればよいでしょうか。
■優先すべき課題の判断基準
・緊急性の高い業務である
・多職種が連携しなければならない
・日常的に起こる事象ではないため、経験が蓄積されにくい
・混乱を防ぐための業務の標準化が必須
といったことが考えられます。
■業務フロー作成のメリット
プラス面は、
・新人教育に適用できる: 経験の浅い職員でも手順を理解できる
・業務内容が常に見える: 次に何をすべきか迷わない
・安心感を持って業務遂行できる: 標準化により不安が軽減
・マイナス面は、
作成までに時間を要する: 初めての作成は特に時間がかかる
図の読み方が分からないと意味がない: 研修が必要
修正が大変: 運用しながらの改善には労力が必要
という点について報告がありました。
そして、関係部署と調整する中で、
・業務の問題点が明らかになる
・「なぜこの手順なのか」を全員が理解できる
・各職種の役割と責任が明確になる
といった点も、作成のメリットと言えます。
作る過程で得られる効果、作った後のメリット、
作成後のアップデートの必要性について学ぶことができました。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)
◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
https://wakuwaku-kokoro.net/
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)
https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A
この記事を書いたのは、こんな人。
ーーーーーーーーーーーーーーー
中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。