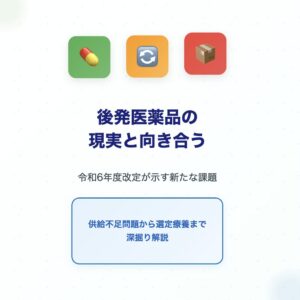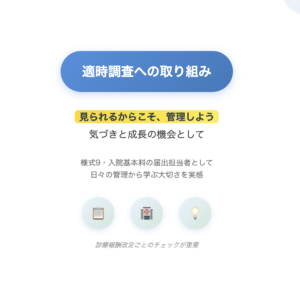【理論と実践】医薬品流通改善ガイドライン改訂〜「総価取引」から「単品単価交渉」へ〜
~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和7年7月15日 医療・介護経営の理論と実践 2619号
■医薬品流通改善ガイドライン改訂〜「総価取引」から「単品単価交渉」へ〜
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。中神です。
■流通改善が新たなステージに突入
令和6年7月、医薬品流通改善ガイドラインが改訂され、
医療用医薬品の取引慣行が大きく変わろうとしています。
改訂の最大のポイントは、これまでの「総価取引」から「単品単価交渉」への完全移行です。
■なぜ今、流通改善なのか
・薬価制度との整合性について
現在の薬価基準制度は銘柄別収載が基本です。
個々の医薬品の価値を反映した価格設定が前提となっています。
しかし、病院と卸との実際の取引では「一括値引き」や「総価取引」が多くみられます。
・安定供給への危機感
後発医薬品の供給不足問題に象徴されるように、
企業努力では対応しきれないような市場、過度な価格競争は、
医薬品の安定供給を脅かしています。
適切な流通コストを確保し、
持続可能な流通体制を構築することが急務となっています。
■「別枠品」という新概念・価格交渉の透明化
今回の改訂で最も注目すべきは「別枠品」の設定です。
基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリーA)、不採算品再算定品など、
医療上特に重要な医薬品は価格交渉の段階から別枠として扱い、
必ず単品単価交渉を行うことが義務付けられました。
これまでの「ベンチマークを用いた一方的な値引き交渉」や
「同一総値引率での交渉」は禁止されました。
個々の医薬品の価値と取引条件を踏まえた適切な価格交渉が求められます。
今回の改訂は、医療機関にとっては、
安易な薬価差益でなく、自院での薬剤の使用方法についてさらなる対策が求められる、
持続可能な医療提供体制の基盤となる取り組みになりそうですね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)
◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
https://wakuwaku-kokoro.net/
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)
https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A
この記事を書いたのは、こんな人。
ーーーーーーーーーーーーーーー
中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。