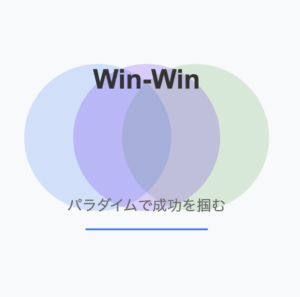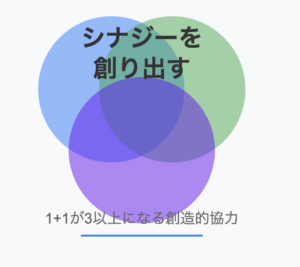【理論と実践】「7つの習慣」第5の習慣:効果的なコミュニケーションの極意
~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和7年2月16日 医療・介護経営の理論と実践 2471号
■「7つの習慣」第5の習慣:効果的なコミュニケーションの極意
中神勇輝(なかがみゆうき)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。中神です。
最近の読み物は、名著「7つの習慣」です。
正式な本の名前は、
「完訳 7つの習慣 人格主義の回復: Powerful Lessons in Personal Change」です。
(スティーブン・R・コヴィー、フランクリン・コヴィー・ジャパン)
ということで、行動に落とし込んでいくために、
一つずつ振り返っていきたいと思います!
■ なぜ多くのコミュニケーションは失敗するのか
私たちは日々、様々な人とコミュニケーションを取っています。
しかし、その多くは表面的なものに留まり、時には誤解を生んでしまうこともあります。
その最大の理由は、
「相手を理解する前に、自分を理解してもらおうとする」
という、私たちの一般的な傾向にあります。
■ 「共感による傾聴」の力
コヴィーは、効果的なコミュニケーションの鍵として
「共感による傾聴」を提唱しています。これは単に言葉を聞くだけでなく、
相手の感情や視点を深く理解しようとする姿勢です。
私たちは往々にして、相手の話を聞きながら、すでに返答を考えています。
しかし、真の理解には、先入観を脇に置き、相手の世界に入り込む勇気が必要です。
■ 5つの傾聴レベル
無視:聞いているふりをする
選択的傾聴:関心のある部分だけを聞く
注意深い傾聴:言葉に集中する
感情的傾聴:感情を理解しようとする
共感的傾聴:言葉の背後にある意味まで理解する
目指すべきは、最も深い「共感的傾聴」のレベルです。
■ 実践のポイント
相手の話を遮らない
助言や評価を急がない
相手の表情や態度にも注目する
「なるほど」「そうだったんですね」など、理解を示す言葉を適切に使う
相手の言葉を言い換えて確認する
■ 理解されるために
相手を理解する努力を重ねた後で、初めて自分が理解される機会が訪れます。
このとき重要なのは、論理的な説明だけでなく、相手との信頼関係や感情的なつながりを基盤とすることです。
■ まとめ
「まず理解に徹し、そして理解される」は、
単なるコミュニケーション技術ではありません。
それは、人との深い関係を築くための哲学であり、生き方です。
この習慣を身につけることで、家族との関係、職場での協力、
そして社会との関わり方が大きく変わっていくことでしょう。
真の理解には時間がかかります。
しかし、その投資は必ず報われます。
なぜなら、人は理解されることで初めて、心を開いて話を聞く準備ができるからです。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)
◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
https://wakuwaku-kokoro.net/
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)
https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A
この記事を書いたのは、こんな人。
ーーーーーーーーーーーーーーー
中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士(登録申請中)、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。